よくわかる!側彎症

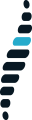 #10高齢の方の側彎症と骨の強度
#10高齢の方の側彎症と骨の強度
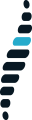


側彎症と骨の強度について
側彎症は背骨が側方に曲がる病気ですが、側彎症が進行した後の手術治療において、骨の強度は非常に大きく関わってきます。特にご高齢で骨が弱くなると、側彎症手術の際に問題が発生することがあります。側彎症の手術では、曲がった背骨をまっすぐに矯正し固定するために、金属製のロッド(棒)やスクリュー(ねじ)等のインプラントを背骨に挿入することが一般的です。しかし骨粗鬆症などで骨が弱くなっている場合、インプラントがしっかりと固定されず、手術後にスクリューが抜けたり、固定が不十分となるリスクが高くなります。そのため、手術を受ける場合は、事前に投薬により骨の強化を行います。
骨粗鬆症とは
骨粗鬆症は、骨の量や質が低下することで骨がもろくなり、わずかな衝撃でも骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症は、女性ホルモンの減少や加齢が原因と言われ、閉経後の女性に多くみられます。また、栄養素の不足や運動不足もリスクを高めます。骨粗鬆症により側彎症の症状も悪化しやすくなる可能性があります。
骨を強くするための日常生活とアドバイス
食事
骨を丈夫に保つためには、食事から必要な栄養素を摂取することが非常に重要です。骨に必要な栄養素はいくつかあり、それぞれの役割を通じて骨をサポートします。
カルシウム
骨の主成分であるカルシウムは、骨の密度や強度を維持するために不可欠な栄養素です。体内のカルシウムが不足すると、骨からカルシウムが溶け出してしまい、骨がもろくなります。カルシウムを多く含む食品には、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、小魚、豆腐、納豆などがあります。毎日これらの食品を積極的に取り入れることで、骨を強く保つことができます。
ビタミンD
ビタミンDは、体内でカルシウムの吸収を助ける働きがあります。ビタミンDが不足すると、いくらカルシウムを摂取しても体に吸収されず、骨が弱くなってしまう恐れがあります。ビタミンDは日光に当たることで皮膚でも生成されるため、適度な日光浴も大切です。食べ物から摂取する場合は、魚類(特に鮭やサバ)、きのこ類、卵黄が豊富な供給源です。
ビタミンK
ビタミンKは、骨のたんぱく質を生成し、骨の質を保つ役割があります。ビタミンKを十分に摂取すると、骨がしっかりとした構造を保ちやすくなり、骨折のリスクも下がります。緑の葉野菜、特にほうれん草やブロッコリーなどが豊富な供給源です。
マグネシウム
マグネシウムは骨の形成をサポートし、カルシウムとビタミンDの働きを助けます。不足すると骨だけでなく、筋肉や神経にも影響が出ることがあります。マグネシウムはナッツ類、豆類、バナナなどに含まれているため、日常の食事やおやつで簡単に摂取できます。
これらの栄養素をバランスよく摂取することが骨の強化に効果的とされ、特にカルシウムやビタミンDを多く含む食品を意識的に摂ることが推奨されます。日常の食事でこれらの栄養素を取り入れて、骨を内側からしっかりと支えましょう。
簡単にできるおすすめの運動
骨を強くするには、運動によって骨に適度な負荷をかけることも効果的です。日常生活に取り入れやすい運動を習慣化することで、骨の強化が期待できます。今回は簡単にできるおすすめの運動をいくつかご紹介します。
ウォーキング
ウォーキングは、特別な器具も場所も必要なく、どこでもできる運動です。歩くことで足や腰に適度な負荷がかかり、骨密度が向上します。特に朝や昼間に歩くことで、日光に含まれる紫外線がビタミンDの生成を促進し、骨の健康を支えます。1日30分程度を目安に、歩く時間を作るようにしましょう。
階段の上り下り
日常生活の中でできるシンプルな運動ですが、階段の上り下りは足や腰に適度な負荷をかけ、骨に刺激を与える効果があります。電車に乗る時や買い物のときなどエレベーターを使わずに階段を利用するだけでも、骨の強化につながります。日常生活の一部に取り入れやすい点も魅力です。
スクワット
自宅でもできるスクワットは、下半身全体の筋力と骨を鍛える運動です。スクワットを行うと、足や腰の骨にしっかりと負荷がかかり、骨の強度が増します。無理をせず、1日10〜15回程度を目安に取り入れると良いでしょう。筋力も同時に鍛えられるため、全身のバランスを保つのにも役立ちます。
骨は適度な負荷を受けることで強くなるため、これらの運動を日常的に行うことで、骨の健康を維持しやすくなります。無理なく続けることが、長期的な骨の強化に効果的です。
手術前の骨強化(治療薬)について
側彎症の手術前に骨を強化する方法として、骨の吸収を抑えたり、形成を促進したりする薬が使われます。特に、骨粗鬆症などで骨がもろくなっている場合は、こうした薬を用いることで骨の質を改善し、手術の際にはインプラントを抜けにくくします。ここでは、骨強化に使われる薬の種類を3つに分けて詳しく見ていきましょう。
※医師の診断のもと、患者さんごとの症状に適した薬を服用していただきます。
1.骨吸収を抑制する薬
骨の吸収がゆるやかになると、骨が減る速度が抑えられるため、骨の形成が追いつきやすくなります。これにより、新しい骨が古い骨の吸収された部分に埋め込まれ、骨密度が高まり、しっかりとした骨が作られます。以下が主な骨吸収を抑制する薬です。
ビスフォスフォネート製剤
破骨細胞という骨を分解する細胞の活動を抑え、骨密度を高める薬です。経口剤や注射剤があり、服用頻度も1日1回から週1回、4週間に1回と幅広く、骨粗鬆症の治療に一般的に使用されます。
女性ホルモン製剤(エストロゲン)
閉経後の骨粗しょう症の治療に有効です。エストロゲンは骨密度の低下を抑える効果があり、更年期の症状を軽減しながら骨粗しょう症を治療します。
SERM(選択的エストロゲン受容体調節薬)
エストロゲンと似た作用で骨密度を高めますが、乳房や子宮などのほかの組織には影響を与えないため、副作用が少なく、骨を選択的に強化します。
カルシトニン製剤
骨吸収を抑える効果と強い鎮痛効果があるため、背中や腰の痛みを抱えている骨粗鬆症患者に用いられることが多い薬です。
デノスマブ
骨吸収に関わる「RANKリガンド」というたんぱく質の働きを抑え、骨の分解を防ぎます。6か月に1回の注射で済むため、継続しやすいことが特徴です。
2.骨の形成を促進する薬
骨の生成をサポートするために、骨形成を促進する薬も多く利用されています。こうした薬は、骨の強度や質を高め、骨折の予防や治療の効果を高めるために重要です。
活性型ビタミンD3製剤
体内でのカルシウムの吸収を高め、骨の生成と吸収のバランスを保ちます。骨粗鬆症の治療に古くから用いられており、カルシウムが骨にしっかりと取り込まれるようサポートします。
ビタミンK2製剤
骨密度を大幅に増やすわけではありませんが、骨形成を助ける作用があり、骨折リスクを減らす効果が認められています。
テリパラチド(副甲状腺ホルモン)
骨を作る骨芽細胞の働きを活性化させ、新しい骨の生成を助けます。骨密度が極端に低く、骨折のリスクが高い患者に使用されることが多く、1日1回の自己注射または週1回の医療機関での注射が行われます。
3.その他の骨強化薬
このほか、骨を強化するために以下の薬も使用されることがあります。
カルシウム製剤
骨の主成分であるカルシウムは、日々の食事から十分に摂取することが難しい場合、サプリメントや製剤として補うことが推奨されます。骨粗鬆症の治療では、食事と合わせて1日1000mgのカルシウム摂取が目安とされています。
手術前の骨強化のポイント
手術に備えて骨を強化するためには、手術の数か月前からこれらの薬の服用を始めることが重要です。特に、ビスフォスフォネートやテリパラチドといった骨密度を改善する薬は、早めに使い始めることで効果が出やすく、骨の質をしっかりと整えておくことができます。また、活性型ビタミンD3やカルシウムの摂取も日常的に意識し、サプリメントなどで不足を補うのも良いでしょう。
